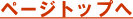開高健さんのことば
戦争、食、釣りをはじめ、人の生きざまをテーマに多くの小説やエッセイを書いた作家で、芥川賞や菊池寛賞などを受賞した開高健(かいこう・たけし)さんという方がいました。
開高さんが亡くなったのは1989(平成元)年12月9日。58歳というご生涯でした。
晩年の16年間を過ごした神奈川県茅ヶ崎市の邸宅は、没後茅ヶ崎市に寄贈され、多くの作品を生み出した書斎や、「哲学の小径(こみち)」がある樹木が生い茂った庭など、当時のままを見学できる開高健記念館となっています。
私が開高作品を読み始めたのは中学生の時でしたが、開高さんがご存命だったら、大江健三郎氏より先にノーベル文学賞を受賞していたはずと信じている作家やファンは今も少なくありません。かく言う私もその一人で、かつて記念館はゆかりの人々が開高さんとの思い出を語る講演会が行われ、かの文豪からいろいろ生き方を学びとろうと通ったものでした。
もちろんこの記念館では、今でも写真や直筆原稿、無数の言葉を生み出した愛用の万年筆をはじめ、書斎などの常設・企画展示物とともに作家の生涯を学ぶことができます。
開高さんのファンの年齢層は幅広く、とある雑誌上では人生相談を通して多くの若いファンとの交流を楽しんでいました。これは著書『風に訊け』にまとめられています。
本書から少しエピソードを拾ってみましょう。開高健(かいこう・たけし)は本名で、作家としての登録名ですが、(かいこう・けん)と言う時もありました。ご本人は〈漢字には音読みと訓読みがあるから「けん」と読まれても返事をするよう努めてきた〉と言いますが、愛用の釣り竿にはなぜか“Ken Kaiko”というサインもありました。
ところがこれが開高さんの言葉遊びのネタにもなっていて、その分析が披露されています。それによると開高健(かいこう・けん)を(かいたか・けん)と読み、さらに(かいた・かけん)に分け、つまり(書いた? 書けん)と、かの「文豪」がしばしば持ち出す話題になっていました。
それからこれは若者から格言についての質問された開高さんが、答えの中で冗談半分に出したような言葉ですが、
〈古今東西有名無名を問わずあらゆる格言のうち、たった一つでもお払い箱になる日は、いったいいつ来るのであろうか〉
というウイットに富んだ格言? を遺しています。
辞書を見ると格言とは人生の真実や機微を述べ、万人への戒め・教訓となるように簡潔にした言葉だと載っており、時空を越えて普遍的な戒めの要素が必要な言葉です。
開高さんは、これまで無数の格言が時代を超えて人々を戒め続けているのに相変わらずの暮らしを続けている人間の様子に、「たった一つでもお払い箱になる日は、いったいいつ来るのであろうか」と言っています。この言葉を考える前に、まずは作家の半生をたどって見たいと思います。
開高さんは少年時代に大阪で第二次世界大戦を経験していますが、1964年から翌年にかけては、朝日新聞社から南ベトナム軍の従軍ジャーナリストとして派遣され、『週刊朝日』の「南ヴェトナム報告」で戦地の模様を日本に伝えていました。これをまとめた著書『ベトナム戦記』や小説『輝ける闇』という本が出版されていますので、現地の人々や兵士たちの悲痛な思いとともに今も詳しく知ることができます。
ベトナムでは兵士たちの悲惨な遺体を見続ける毎日を過ごしていた開高さんでしたが、ある日ジャングルでゲリラに包囲され猛攻撃に遭い、部隊総勢200人中17人しか生還できなかったうちの一人として帰国します。その壮絶さは35歳にして〈あれ以降の人生は、おまけみたいなもの〉と語り、反戦活動にも参加しました。

命へのこだわり
そういう開高さんですが、帰国後は生きるということにこだわっていたようです。
その一つが、辻調理師学校の創設者である辻静雄氏やサントリーの会長をつとめた佐治敬三氏らと交友関係があったからでしょうか、国内のみならず仕事で旅をして世界中の美味、美酒を豪快に飲食するということに表れていたようです。開高さんは美味同様、滋味(深い味わい、滋養のある食べもの)、時には魔味(人を惑わす不思議な味わい)という言葉も使っていました。
一方で食と言えば『新しい天体』という小説では、主人公の役人が景気と食の質との関連性を調査する目的で日本全国の美味を全て食べきった後に行き着いたのは、山のわき水だったと書いていたり、色紙には「心に通ずる道は 胃を通る」というイギリスのことわざを書いたりしていました。茅ヶ崎市内にある町の洋食屋さんの常連だったという開高さんですが、ただ美味しいものを食べて満足していたわけではなさそうです。
ちなみに開高さんが世界の釣り紀行番組をされていた時に、現地での食事や釣った魚を調理するため同行していた調理担当は、辻調理師学校の谷口博之教授でした。記念館で谷口教授が講演されると聞いて私も記念館に行き、何日も魚が釣れず日本から持ち込んだ食料も少なくなってきた時、乾麺のそばをゆでたら嬉しそうに食べていた話や現地で釣った魚の調理法や開高さんの感想など、興味深く聞かせていただきました。
釣りと言えば、開高さんは釣り針をくわえもがいている魚を〈あれは私自身だ〉と表現して自らの生きざまを魚に重ね合わせたり、川にできた大きな蚊柱(かばしら・多くの蚊が群れをなして、まるで柱を立てたように飛んでいる様子)を見ては、自然界の命の営みに心を打たれていたりと、その様子が映像に残っています。
「キャッチ・アンド・リリース(釣った魚を放流する)」という思想を広めたのも開高さんだと言われています。ご本人によれば、〈(登山者は)山に登りたくて登るのであって、高山植物を折るために登るわけではない。川や森を知るために釣りをするのであって、魚(の命まで)はとりこまなくていい〉とのことです。
全て放流していたわけではありませんが、開高さんにとっての釣りとは生態系を広く見つめ、人間の知恵をしぼって釣りを通して自然に挑むことで、自然の中にいる自分を実感するためのものであり、むやみに命を奪うことを目的にしたわけではないということなんだろうと思います。
また著書『私の釣魚大全』で、日本が江戸時代の頃、イギリスではすでに将来を見越してその川のそのエリアの1日あたりの鮭の魚獲規制が設けられていたと語っています。
こういう目の付けどころはご自身の作家活動にとどまらず、こんなことにも表れます。
昭和40年代前半から始まった釣りブームで、開高さんも通った福島と新潟の県境に位置する奥只見(おくだだみ)に釣り客が押し寄せ、天然の巨大イワナやヤマメなどの数が激減し、同時に原生林の荒廃が見られるようになりました。
昭和49年、地元民や開高さんの釣りの師匠であった常見忠氏ら釣り人たちを中心に、人間が荒らした自然を元に戻そうと、漁獲規制や禁漁期間の延長、さらには稚魚の放流を地元漁協に嘆願する会の設立が計画されます。発起人の1人であった開高さんは発起人代表となり、翌年「奥只見の魚を育てる会」として正式な発足と同時に初代会長となりました。
〈人間が一歩進むと自然は音もなく二歩後退します〉と、同会事務局長となった常見氏や地元民らとともに働きかけ、これに行政も反応して川には次第に魚影が戻るようになります。
平成16年に事務局が魚沼市観光課に移管されるまで、当地では会の嘆願を上回る自然保護が展開されていきました。これは我が国における環境保護活動の先駆けとも言えるでしょう。
開高さんは没後同会の永久会長になりましたが、生前の偉業を讃え、第二代会長となった常見氏ら有志により、会の活動によって永久保護河川となった北ノ又川に記念碑が建てられました。そこには川はいつも命を育んでいるという開高さんの言葉「河は眠らない」と刻まれています。
こうしてみると、開高さんが目を向けたのは、小説に登場するような人の営みだけではなく、あらゆる命の大事を考え、訴え、行動した作家であったと言える気がします。

遠い道を ゆっくりと けれど休まずに 歩いていく人がある
さて、そういう開高さんが遺した〈古今東西有名無名を問わずあらゆる格言のうち、たった一つでもお払い箱になる日は、いったいいつ来るのであろうか〉という言葉を、私たちはどう考えたらいいでしょう。
開高さんの小説『白いページ』に〈石器時代から人間というやつは自明の理が大の苦手ときていて、大火傷を負ったり負わされたりしないことにはそこへたどりつけないときている〉という言葉があります。大自然に育まれている一種類の生きものにすぎないのに、本質的な部分で有史以前から現在に至るまで、相変わらず欲の突っ張り合いをしながら暮らし、争いを起こし続け、自滅の道を歩んでは後悔して引き返すのを繰り返しているのが人間ということでしょうか。それではいつまでたっても〈お払い箱になる日〉は来ないでしょうね。
そう聞くと、何か頼りになるものがほしいところ、と思ったあなた、
少なくとも2500年も前から、先祖代々全然きわめ尽くせない教え「永遠に滅することのない仏さまのお心」が、私たちに寄り添ってくれていることを忘れていませんか?
お釈迦さまがこの世でご活躍されたのは2500年くらい前ですが、仏教は今も続いています。
ということは古今東西の格言同様、その時以来1つとしてもはや不要と言える仏さまの教えもないと言えるはずです。つまり仏教はいつの時代でもそういう私たちに歯止めをかけ続け、導き続けてくれているのではないかと思います。
さらに仏教では何度も生まれ変わって修行を積み、いずれ悟りの境地にいたると説かれます。これを輪廻(りんね)と言いますが、開高さんは鮭の産卵場となった川で子孫を残すつとめを終えて朽ち果てていく親の魚体を見て〈命の輪廻が信じられる気がする〉と言っています。
しかし自然界の生きものはただ輪廻するだけではなく、気温などの地球環境の変化に対応できるよう成長・進化し命を受け継いでいます。
鮭の例を見るまでもなく、私たち人間の命も同様に受け継がれており、私たちもまた過去より現在、現在より未来に、成長・進化し続けなければ破滅はまぬがれないでしょう。
そうなると私たちに必要なのは、教えを学ぶことであり学んだら及ばずながらも実践にうつし、教えの意味を実感できたらそれに応じて自分の心を修正し洗練させ、さらに暮らしに仕事に創意工夫を重ねていく。これが教えを自分のものにする、活用していくということです。言葉を換えれば日々の修行です。そしてもう一つ大事なのが、いただいた教えをたくさんの人々と共有していくこと。
私はこれが〈たった一つでもお払い箱に〉する方法ではないかと思います。
まあ、何をしたからと言って急に変わるものでもないでしょうが、開高健記念館にいくつかある文学碑の中には「遠い道を ゆっくりと けれど休まずに 歩いていく人がある」というのがあります。
ただでさえ地球上に人類が現れたのは700万年前だそうですが、私たちは進化しながらもそれだけの年月をかけて今の社会を作っています。しかも今はただでさえ慌ただしい世の中です。私はこの言葉のように、ゆっくりしかし着実にという心構えでいいのだろうと思っています。そしてゆったり構えながらもチャンスは確実に(開高さん流に言えば〈悠々として急げ〉)です。
年の瀬に、来年に向けてと考え始めたら開高さんが思い出されました。
ちなみに来年のいまごろは、かの文豪の第27回忌です。
それまでに世の中の格言をせめてたった一つでも、たとえ私個人の振る舞いであっても、お払い箱にできるヒントくらいは見つけたいもの。なんて実は13回忌の時にも思ったんですが、来年も「そういう日はいったいいつ来るのであろうか」ってつぶやきながら過ごしてるんだろうな、きっと。
今年もお世話になりました。
みなさまよいお年を。
写真は上から開高健著『ベトナム戦記(朝日文庫)』、『風に訊け上・下(集英社)』、開高健記念館
開高健 格言について
開高健 格言